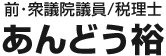ひろしの視点
HIROSHI’S POINT OF VIEW
ひろしの視点
2019/03/19
イギリスのEU離脱の行方
~英国内で起きていることと、グローバリズムの弊害~
イギリスのEU離脱が混迷しています。
ご承知のとおり、メイ首相が提案した離脱案は議会で否決され、その後修正案を提示しても可決できる見込みは極めて低くなっています。
これにより、合意なき離脱が現実となり、その後のイギリスとEUとの貿易をはじめとするあらゆるモノやヒト、カネの動きは相当混乱することが予想されます。
しかし、イギリスのEU離脱は、実は将来の英国にとっては良い選択である、ということができます。グローバル化が進展し、ヒト・モノ・カネの動きを自由にすれば、必ず経済成長して皆が豊かになれる。そういう発想でヨーロッパの経済統合は進められてきました。
しかし、EU圏内では、いま貧富の差が拡大し、さらに移民問題も大きな課題として浮上してきました。移民問題は、以前から存在していましたが、なかなか表には出て来なかったのです。というのは、移民を政治課題や社会問題として発言すると、「人種差別者だ!」とか「古い考え方だ!」「国粋主義者だ!」「極右だ!」みたいなレッテルを貼られてしまい、発言が封じられてしまい、冷静な議論ができなくなってしまうからです。
最近日本で発売された「西洋の自死」という本があります。これは、原題は「THE STRANGE DEATH OF EUROPE」ですから、直訳すれば「ヨーロッパの奇妙な死」となるのですが、文字通り、ヨーロッパはいま移民によって元々のヨーロッパとは異なるものに変貌しつつある、というのです。
どういうことか。この本の冒頭部分を書き出してみましょう。
「欧州は自死を遂げつつある。少なくとも欧州の指導者たちは、自死することを決意した。欧州の大衆がその道連れになることを選ぶかどうかは、もちろん別の問題だ。
私が「欧州は自死の過程にある」と言うのは、「欧州委員会の規制の重みが耐えがたくなっている」という意味でもなければ、「欧州人権条約がある特定のコミュニティを十分に満足させてこなかった」という意味でもない。「私たちの知る欧州という文明が自死の過程にある」という意味である。英国であれ西欧の他のどの国であれ、その運命から逃れることは不可能だ。なぜなら我々は皆、見たところ、同じ症状と病弊に苦しんでいるからである。結果として、現在欧州に住む人々の大半がまだ生きている間に欧州は欧州でなくなり、欧州人は家と呼ぶべき世界で唯一の場所を失っているだろう」
出だしから衝撃的な書き出しなのですが、その後、英国の様子が書かれている部分があります。それも長いですが、一部抜き出してみます。
『少数派になった「白人の英国人」』
「欧州で進行しつつある変化の規模と速度を理解するには、ほんの数年ほど時代をさかのぼり、現在の移民危機が発生する以前の、「正常な」移民が行われていた時期に立ち返ってみることが有効だ。また最近の混乱からは多少なりとも距離があった頃の国家について考察することも無駄ではあるまい。
2012年に英国内のイングランドとウエールズにおける最新の国勢調査の結果が発表された(調査の実施は前年)。そこには前回の国勢調査以降の10年間で、英国がどれほど変わったのかが示されていた。ここで2002年当時のある人物が、その国勢調査から見出した事実を基に、次の10年間を予測したと仮定しよう。その人物が次のように語ったとしたらどうか。「今後10年以内にこの国の首都では白人の英国人が少数派となり、イスラム教徒の人口が倍増するだろう」
こうした言説が果たしてどのように受けとめられただろうか。「心配性」「人騒がせ」といった言葉が間違いなく向けられ、果ては「人種差別主義者」や当時は新語だった「イスラモフォビア(イスラム嫌い)」のそしりを受けていた可能性も高い。いずれにせよ、そうした予測が温かく迎えられなかったことは確実だろう。疑う向きはその典型例を一つだけ思い起こしてみるとよい。2002年に「タイムズ」紙のある記者が将来の移民の動向に関して上記よりはかなりトーンを抑えた予想を書いたところ、デビット・ブランケット内相(当時)から「ファシズムすれすれ」だと糾弾されたのだ。
だがどれほど批判されたにしても、2002年にそのような分析を行った人々は完全かつ全面的に正しかった。2011年に実施され、2012年末に結果が公表された次の国勢調査によって、上記ばかりか、それを遥かに超える事実までが明らかになったのだ。イングランドとウエールズの居住者中、国外で生まれた人々の数は、直近の10年間で300万人近く増えていた。またロンドンの住民の中で、自らを「白人の英国人」と回答した人々はわずか44・9%だった。さらにイングランドとウエールズに住む人々のうちの300万人近くは、英語を主たる言語とする成人が1人もいない家庭に属していた。
これらは歴史的に見ても、一国の人種構成として極めて大きな変化ではある。英国ではしかし、宗教から見た人口構成に関しても同じように特筆すべき変化が起きていた。たとえば同年の国勢調査では、キリスト教を除くほとんどすべての宗教で信者数が増えていることが明らかになっている。昔ながらの英国の国民的宗教だけが唯一、急激に衰退しているのだ。前回の国勢調査以降、自分はキリスト教徒であると回答した住民の割合は72%から59%に低下した。イングランドとウエールズに住むキリスト教徒の実数は400万人以上も減少し、3700万人から3300万人へと落ち込んだ。
キリスト教徒の信者数が激減するーそして今後も減り続けるだろうと予想されるー一方で、イスラム教の信者数は、移民の大量流入の影響もあって2倍近くに増えていた。2001年から2011年の間に、イングランドとウエールズに住むイスラム教徒の数は150万人から270万人に増加している。しかもこれは公式な数値に過ぎず、不法移民も含めればその数はもっとずっと多くなるはずだ。英国に不法入国したーつまりは国勢調査に回答する可能性の低いー人々は、少なくとも100万人はいると考えられる。また、最も急速にイスラム教徒数が増えた二つの自治区(10年間で20%以上の増加)は、そもそも英国きってのイスラム人口を抱えていたところだった(ロンドンのタワーハムレッツ区とニューハム区)。両区が属しているのは国勢調査に回答しない住民が英国内でも最も多い地域で、およそ5世帯に1世帯が未回答だ。これらすべてが示唆しているのは、ただでさえ目をむくような国勢調査の結果すら、実際の数字を大幅に下回っているだろうということである。それでもなお、そこから見えてきたものは衝撃的だった。
だが、1年かけても分析しきれないほどの内容だったにもかかわらず、国勢調査の話題はー一過性のニュースが総じてそうであるようにー2日もすると忘れられた。問題は、これが一過性の話題などではなかったことだ。それは英国の直近の過去と、直面する現在を説明するものであり、また避けがたい未来を垣間見せるものでもあった。
その国勢調査結果を分析すれば、どうにも動かしようのない一つの結論が見えてくる。すなわち大量移民は英国をまったく違うものに変えつつあるということだ(実際、すでに変えた)。2011年の英国は、もはや何世紀にもわたって続いてきた英国とはまるで異なる場所になっていたのだ。しかし、たとえばロンドンの33区中23区で今や「白人の英国人」が少数派になっているといった事実に対しては、国勢調査結果それ自体と同様に前向きな反応が寄せられた。英国の国家統計局(ONS)のあるスポークスマンは、この調査結果を大いなる「多様性」の表れだと歓迎している。
一方、政界とメディアの反応は、驚いたことにたった一つのトーンに凝縮されていた。主要な政党の政治家は皆、同年の国勢調査結果に対し、等しく祝福を送ったものだ。それは何年も前から変わらぬ風潮だった。2007年には当時のロンドン市長のケン・リビングストンが、ロンドンで働く人々の35%が外国生まれであるという事実を誇らしげに語っている。残る問題は、そこに最適な限度があるのかという点だった。ここ何年もの間、英国の変化に対して期待と楽観以外の感情を示すのは不適切であるかのような雰囲気があった。それを下支えするために、これは別に目新しい現象ではないのだという弁明がなされてきた。」
ダグラス・マレー著
中野剛志解説/町田敦夫訳
東洋経済新報社/2018/12/14刊
移民が英国という国柄を大きく変えてしまっている。私たち日本人から見れば、英国は「白人のキリスト教徒の国」というイメージがありますが、実態は大きく変貌しつつある。ロンドンでは白人は少数派になり、キリスト教徒は減少し続け、イスラム教徒が急速に増えつつある。しかも、エリート層はこれらの変化を「歓迎」するコメントを出し続けるのです。
そして、これら移民の受け入れは次の理由で正当化されると分析されています。
- 大規模な移民は我々の国々の経済を利する
- 高齢化する社会では移民を増やすことが必要だ
- いずれにせよ移民は我々の社会をより文化的で、興味深いものにする
- たとえ上記がすべて誤りでも、グローバル化が進む限り、大量移民は止められない
いま、日本でも入国管理法が改正されて外国人労働者の受け入れが拡大することが決定しましたが、日本でも同様の議論がなされたことは皆さんもご承知の通りです。
そして、日本の国会での議論は、外国人労働者の人権の話は議論されたものの、日本人社会にどのような影響を及ぼすのか、日本人社会を守るためにはどういう対策が必要か、といったことについては一切議論がされませんでした。将来の日本が、この本の英国のように変化していく恐れは多分にあります。しかし、エリート層の発言は、「少子化なので外国人の受け入れはやむを得ない」「多文化共生社会の実現は日本にとってよいことだ」「労働力不足が日本の経済成長の足かせになる」「グローバル化は避けられない。日本は鎖国していてはならない」という論調が主流になっています。まさに、この本の指摘通りの議論が日本でも行われているのです。
日本の報道では、イギリスのEU離脱はとんでもない選択である、という論調で報道されています。しかし、これらの実際に起きている現象を見ると、離脱の選択をするのは合理的な選択であるということができます。
問題は、離脱に至る道筋が極めて不透明で、混乱をきたす恐れがあるということです。離脱の道筋さえしっかりつけることができれば、英国内の混乱も一時期よりは落ち着き、経済的にも成長するでしょう。(EUから離脱すると英国が経済的に困窮するというのは当たらないと思います。なぜなら、英国がEUから離脱した後もEUと貿易するということは、日本や米国と同じ条件でEUと取引する、ということに他ならないからです。日本も米国も、EUに加盟していなくても普通に取引をしています。日米と同じ条件になるというだけの話です。)
恐らく、離脱することによって英国の労働者の賃金は上がり、関税が復活するので国内産業は保護され不当な安値で取り引きをしなくてはならない事態から解放されるでしょう。英国は通貨統合までしていなかったのが幸いし、財政政策も自由にとることができるので、経済政策も自由に英国民のために行うことができるようになります。問題は、それまでの移行コストがどの程度かかり、それに政治的なエネルギーをきちんと割くことができるかどうかという点だろうと思います。
EUでは、英国に続いて各国で離脱運動が大きくなりつつあります。フランスでも黄色いベスト運動が大きくなってきていますが、この運動も反グローバリズム運動です。日本では極右のおかしな政治団体の活動のように報道されていますが、実際は静かなデモを行っているようで、でも主張は決して極右ではなく、極めてまっとうな権利の主張であり、健全なナショナリズムを取り戻す運動であるようです。
世界の反グローバリズムの動きをどう捉えるべきなのか。日本も真面目に考えなくてはなりません。
-「ひろしの視点」第53号(2019年1月)より-